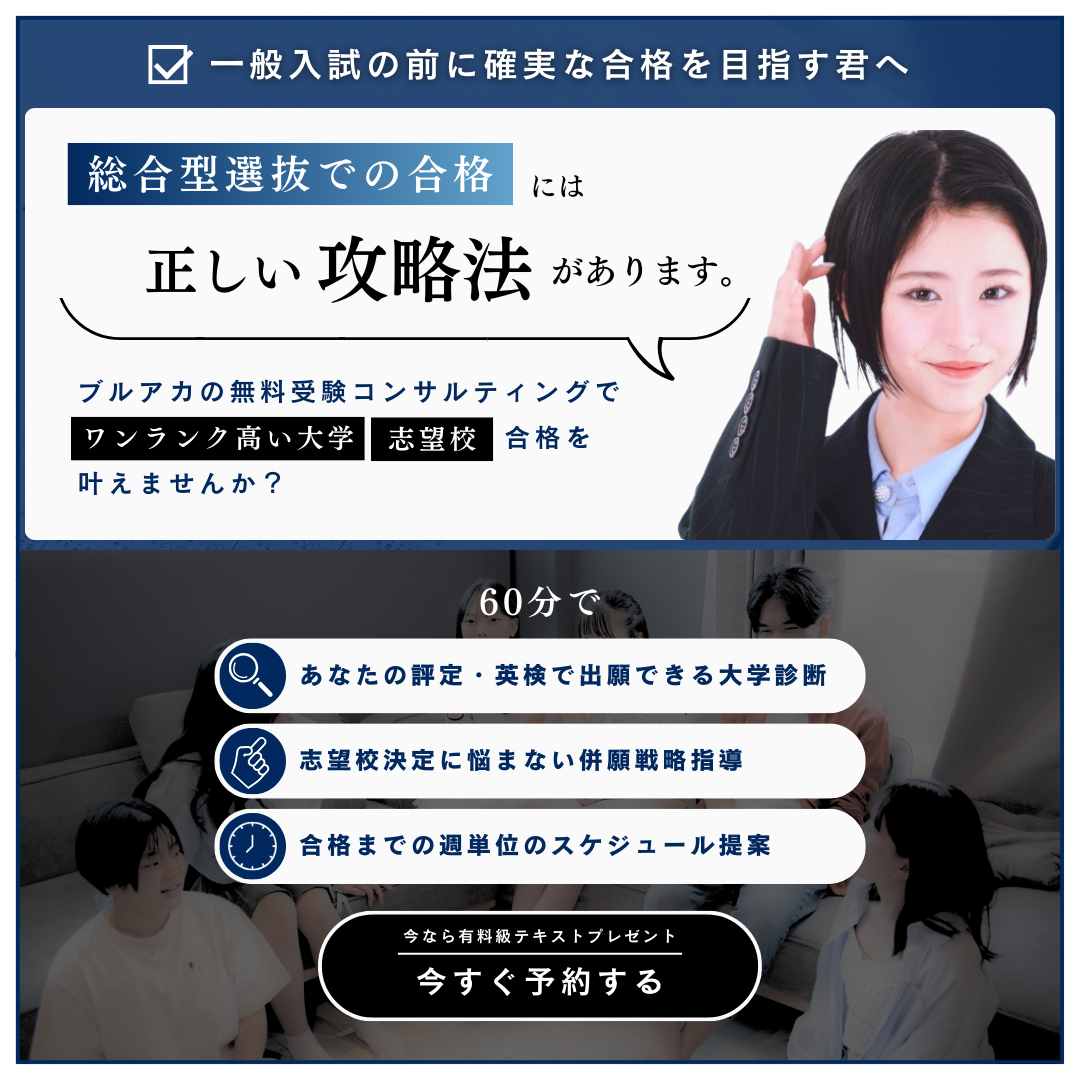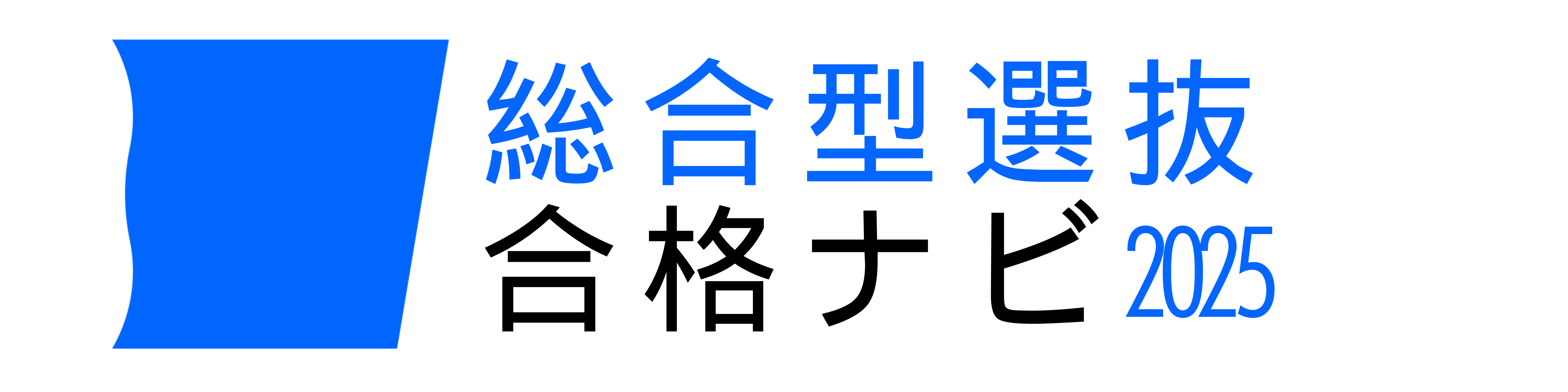本記事は総合型選抜対策塾ブルーアカデミーよりお送りしています。
本日は、「MARCH vs 関関同立 徹底比較」というテーマで、学費、受験難易度、キャンパスライフなど、様々な面から比較していきます。
本記事とは別で、それぞれの大学、学部ごとの記事も多数ご用意していますので、是非そちらもご覧になっていただければと思います。
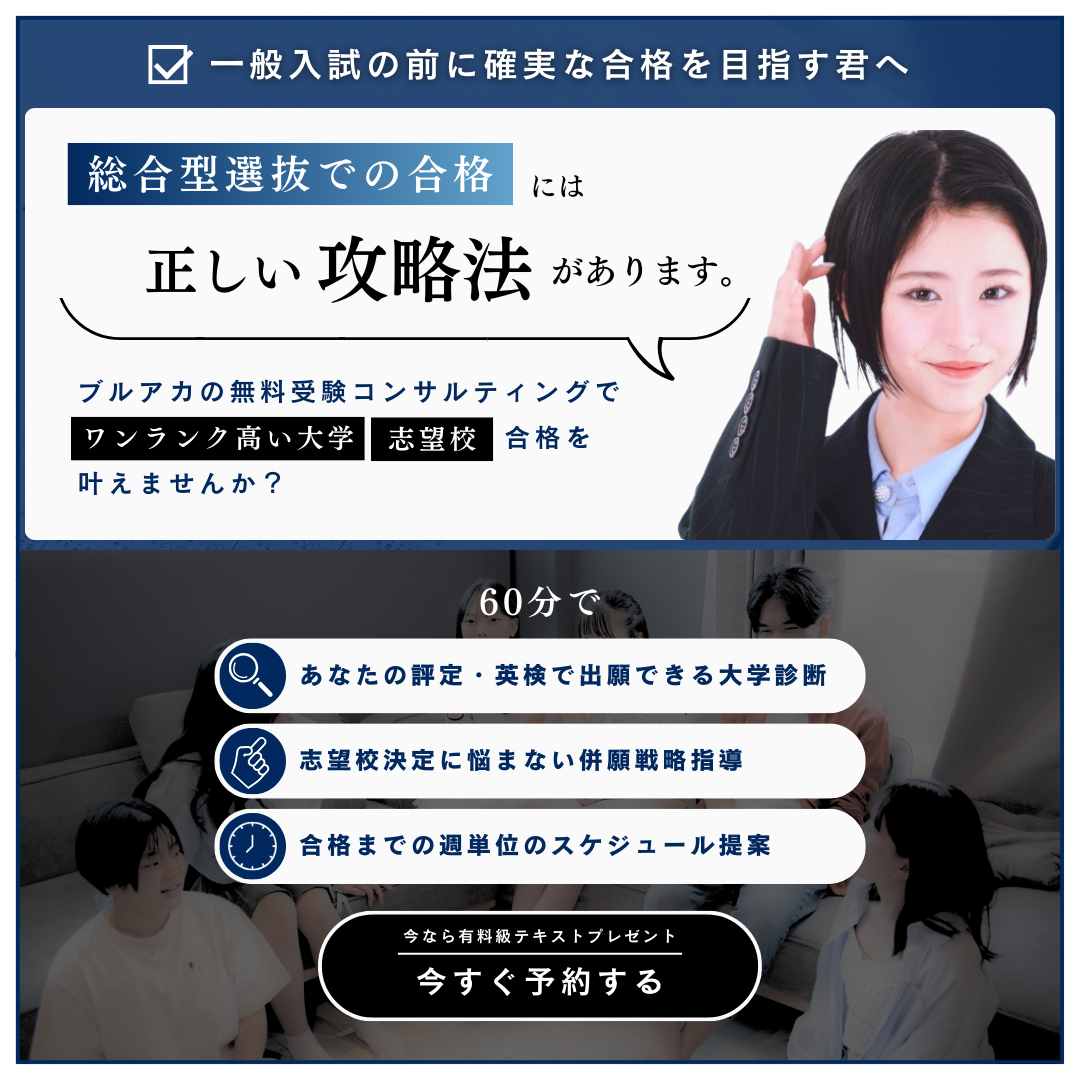
基本情報(大学の特色・学部・学生数・学費)
関東の人気難関大学群!MARCH
MARCHは首都圏(主に東京都)を拠点とする難関私立大学群で、以下の5大学の総称です。
M:明治大学
1881年創立の伝統校で、法学部などが看板です。都心キャンパスを中心に、理系は郊外キャンパスに配置しています。
学部数:10
学生数:約32,730人(MARCH最多)
A:青山学院大学
キリスト教主義の学校で国際色豊か。「英語の青学」とも称され、航空業界への就職者が多い点が特徴的。キリスト教主義の学校で国際色が豊かです。
学部数:11
学生数:約19,677人
R:立教大学
プロテスタント系ミッションスクールで、池袋の本キャンパスは歴史的建造物にツタが絡む風情。異文化コミュニケーション学部など国際系に力を入れています。
学部数:12
学生数:約20,531人
C:中央大学
法学部は国家試験合格者数で著名で、公務員志向の学生も多い。多摩の広大なキャンパスに文系学部を集約し、都心(後楽園)に理工学部キャンパスなどを持ちます。
学部数:8
学生数:約26,669人
H:法政大学
明治・中央と並び1880年代創立の総合大学。多彩な学部(キャリアデザイン学部など特色ある学部含む)を持ち、キャンパスは市ヶ谷や多摩など複数あります。
学部数:15(MARCH最多)
学生数:約28,618人
関西の人気難関大学群!関関同立
一方で、関関同立は関西圏を代表する難関私立大学群で、以下の4大学から構成されます。
関:関西大学
1886年創立(旧「関西法律学校」)で法学分野で長い歴史を有する大学。マンモス校として関西では高い人気を誇っています。
学部数:14
学生数:約27,918人
関:関西学院大学
通称「関学」。オシャレなキャンパスと国際的な環境が人気の大学です。
学部数:14
学生数:約24,737人
同:同志社大学
キリスト教の大学で関西圏の私大ではトップレベル。関関同立の4つの大学の中でも特に評価が高くなっています。
学部数:14
学生数:約26,514人
立:立命館大学
第二次大戦後に学生数を急拡大したマンモス大学。京都市北西部の衣笠のほか、大阪の茨木や滋賀県のびわこ・くさつにキャンパスがあります。
学部数:16 (関関同立最多)
学生数:約38,657人(関関同立最大)
徹底比較【学費】
学費面は両大学群とも私立大学平均よりやや高めですが、大きな差はありません。MARCHの4年間の学費総額は文系:約440〜500万円、理系:約600〜680万円程度で、文系より理系の方が高額です。
特に青山学院大学と立教大学はMARCH内ではやや学費が高めと言われます。
関関同立も文系4年間で約440〜460万円、理系では大学や学部によって600万円以上かかる場合があります。例えば関西学院大学・立命館大学は他に比べ学費がやや高めで、同志社大学は平均的、水準。いずれも国公立に比べれば高額ですが、設備や留学制度など充実した教育環境が整っています。
徹底比較【偏差値・難易度】
MARCHと関関同立はレベル的にほぼ同等とされ、様々な場面で比較されがちです。まず分かりやすい偏差値の面で比べてみましょう!
MARCHの方がやや難しい
結論、全体的な偏差値水準はMARCHがやや上だと言えるでしょう。
実際、MARCHと関関同立の9大学を合わせた偏差値序列では、上位5校中4校をMARCH勢が占める結果が出ています。
| 大学 | 偏差値 |
| 立教大学 | 62.5 |
| 同志社大学 | 62.5 |
| 青山学院大学 | 62.0 |
| 明治大学 | 61.5 |
| 中央大学 | 59.0 |
| 関西学院大学 | 58.5 |
| 関西大学 | 58.5 |
| 立命館大学 | 57.0 |
| 法政大学 | 56.0 |
(参照:https://reashu.com/march-vs-kankandouritsu/)
これは首都圏には早慶上智といったMARCHより上位の私大が存在し、受験層が厚いためMARCHの偏差値も自然と引き上げられている一方、関西では関関同立が私大トップであることが背景にあるようです。
MARCH内の難易度差では、立教大学が平均62.5で最難関(同志社と同水準)。次いで青山学院(62.0)、明治(61.5)、中央(59.0)、法政(56.0)の順となっています。立教は看板の異文化コミュニケーション学部などが高倍率で知られています。もっともMARCH各校の差は小さく、明治・青学・立教のトップ3校は互いに僅差です。
他方、関関同立内の難易度差では、同志社大学が頭一つ抜けて難しく、偏差値平均62.5で単独トップ。続いて関西学院大学・関西大学(ともに58前後)、立命館大学(57前後)と続きます。同志社は文系学部の偏差値も軒並み60超えと高水準で、特に神学部・文学部・心理学部など人文系が高めです。
文系と理系で見る偏差値傾向としては、一般的に理系の方がやや低めに出ることが多いですが、両大学群とも理系でも60前後の学部が多く文系に引けを取らない水準です。例えば明治大学は文系学部偏差値が概ね63〜67、 理系学部は60〜66程度。関西大学も文系57.5〜60に対し理系(システム理工など)で50〜55と開きがありますが、多くの学部で偏差値50台後半〜60台をキープしています。
なお合格難易度を測る指標としては各大学の入試得点率や倍率も参考になりますが、ここでは割愛します。総じてMARCH>関関同立の構図はあるものの、その差は大きくなく、いずれも偏差値60前後が中心で「難関大学」と呼ぶにふさわしいレベルと言えるでしょう。同志社や立教など一部学部では偏差値65超も見られ、早慶やGMARCH(学習院を含む)に匹敵する難易度のところもあります。
徹底比較【就職力】
続いては、MARCHと関関同立の就職力に着目して比較していきたいと思います。
両グループとも「就職に強い大学」として知られ、毎年高い就職実績を誇ります。特に大手・有名企業への就職率や卒業生の平均年収などで見ると、MARCHと関関同立の差はほとんどありません
まずは、MARCH、関関同立それぞれの主な就職先を見ていきたいと思います。
今回は簡略化のため、それぞれの大学の「経済学部」の学生の就職先をご紹介します。
MARCH
明治大学政治経済学部
| 東京特別区、みずほフィナンシャルグループ、国家公務員(一般職)、(株)NTTドコモ、(株)ジェーシービー、りそなグループ、アクセンチュア(株)、大和証券(株)、東京都庁、日本電気(株)、EY新日本有限責任監査法人、(株)商工組合中央金庫、住友不動産販売(株)、有限責任監査法人トーマツ、三井住友信託銀行(株)、(株)三菱UFJ銀行、アビームコンサルティング(株)、(株)NTTデータグループ、キーエンス、ソフトバンク(株)、(株)ニトリ、野村証券(株)、(株)三井住友銀行など |
青山学院大学経済学部
| みずほ証券(株)、(株)きらぼし銀行、富士通(株)、(株)みずほ銀行、(株)リクルート、キャノンITソリューションズ(株)、(株)ジェーシービー、大和証券(株)、TIS(株)、(株)電通デジタル、日本生命保険相互会社、(株)ベイカレント・コンサルティング、三井住友信託銀行(株)、(株)りそなホールディングスなど |
立教大学経済学部
| 株式会社ジェーシービー、株式会社みずほフィナンシャルグループ、東京都特別区、りそなグループ、株式会社NTTデータグループ、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、レバレジーズ株式会社、損害保険ジャパン株式会社、日本電気株式会社(NEC)、東京海上日動火災保険株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、日本生命保険相互会、社デロイトトーマツコンサルティング合同会社、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社株式会社サイバーエージェント、富士通株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社など |
中央大学経済学部
| りそなホールディングス、みずほフィナンシャルグループ、ジェーシービー、NECソリューションズイノベータ、中央労働金庫、レバレジーズ、伊藤忠テクノソリューションズ、国税庁、東京都庁、東京海上日動火災保険、商工組合中央金庫、太陽生命保険、富士フイルムビズネスイノベーションジャパン、ニトリなど |
法政大学経済学部
| YKK AP株式会社、いすゞ自動車株式会社、TOPPANホールディングス株式会社、株式会社東芝、沖電気工業株式会社、日本電気株式会社(NEC)、株式会社IHI、本田技研工業株式会社、株式会社ファーストリテイリング、株式会社ニトリ、JFE商事株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社横浜銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社千葉銀行、株式会社三菱UFJ銀行、大和証券株式会社、株式会社静岡銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社SBI新生銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、りそなグループ、株式会社りそなホールディングス、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、アフラック生命保険株式会社、住友生命保険相互会社東京本社、第一生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)、日本放送協会(NHK)、株式会社サイバーエージェント、株式会社リクルート、NECソリューションイノベータ株式会社、株式会社NTTデータグループ、株式会社日立システムズ、株式会社JTB、株式会社ニトリホールディングス |
関関同立
関西大学経済学部
| アクセンチュア、有限責任あずさ監査法人、西日本高速道路(NEXCO西日本)、パスコ、阪神高速道路、ベイカレント・コンサルティング、アイシン、アイリスオーヤマ、イシダ、いすゞ自動車、伊藤ハム、イトーキ、関西ペイント、キーエンス、京セラ、キリンホールディングス、クボタ、グンゼ、神戸製鋼所、ンテック、NECソリューションイノベータ、NECフィールディング、NSD、大塚商会、オービック、スミセイ情報システム、DTS、日本総合研究所、国家公務員一般職、滋賀県職員、大阪府職員など |
関西学院大学経済学部
| 清水建設、一条工務店、竹中工務店、日本たばこ産業、アサヒ飲料、サントリーホールディングス、NTTドコモ、レバレジーズ、日本IBM、マイナビ、富士通エフサス、Sky、ヤフー、サイバーエージェント、ANAエアポートサービス、ニトリ、良品計画、三井住友信託銀行、京都銀行、ジェーシービー、アコム、損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、ソニー損害保険、オープンハウスグループ、日本赤十字社、日本M&Aセンター、有限責任(監査)トーマツ、ベイカレント・コンサルティング、国家公務員、裁判所など |
同志社大学経済学部
| 国家公務員(一般職)、株式会社京都銀行、ベイカレント・コンサルティング、村田製作所、東京海上日動火災保険、みずほフィナンシャルグループ、ニトリ、パナソニック、京セラ、アクセンチュア、三井住友信託銀行、日立製作所、三菱電機、レバレジーズ、キーエンス、リクルート、サイバーエージェント、有限責任監査法人トーマツ、日本IBM、大和証券、野村証券、AGC、PwCコンサルティング、マイナビ、イオンリテール、ユニクロ、TOTO、JFEスチール、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ、伊藤忠丸紅鉄鋼、農林中央金庫、味の素、アマゾン・ジャパン、電通デジタルなど |
立命館大学経済学部
| 有限責任あずさ監査法人、川崎重工業、関西電力、キーエンス、京都銀行、JTB、滋賀銀行、シャープマーケティングジャパン、大和証券グループ、有限責任監査法人トーマツ、トヨタ自動車、NTT西日本、日本年金機構、ニトリ、日本生命保険相互会社、野村証券、パナソニックホールディングス、富士通、船井総合研究所、ベイカレント・コンサルティング、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、村田製作所、ローム、国家公務員一般職、国税専門官、地方公務員(上級)など |
以上がMARCH、関関同立の各大学の経済学部生の主な就職先となっています。
上位15%の大学群ということもあり、一度は聞いたことのある有名企業への就職者が多くいることが分かります。
実際の各大学の有名企業への就職率のデータも以下でご紹介します。
MARCH5大学有名企業就職率
| 大学名 | 有名企業への就職率 |
| 明治大学 | 29.8% |
| 青山学院大学 | 26.5% |
| 立教大学 | 26.0% |
| 中央大学 | 24.2% |
| 法政大学 | 20.8% |
関関同立4大学有名企業就職率
| 大学名 | 有名企業への就職率 |
| 同志社大学 | 32.5% |
| 関西学院大学 | 24.9% |
| 立命館大学 | 21.9% |
| 関西大学 | 18.4% |
(参照:https://univpressnews.com/2024/12/17/post-16155/)
上の表の通り、MARCHと関関同立はいずれも約4〜5人に1人が有名企業へ就職しており、平均値でもMARCH=25.5%、関関同立=24.4%とほぼ互角です。例えば同志社大学は約32.5%(全国14位)で群内トップ、明治大学も約29.8%と健闘しています。
関関同立内訳を見ると同志社32.5% > 関学24.9% > 立命21.9% >関大18.4%と差がありますが、これは同志社の学生層・実績が群を抜いているためです。一方MARCHも明治約30%、青学約27%、立教26%、中央24%、法政21%と分布します。
要するに「MARCHと関関同立、どちらが就職で有利か?」という問いに対しては、「数字上はほぼ同じ」と言えるでしょう。
平均年収の面でも同様です。転職サービスDODAの調査によれば、MARCH卒業生の平均年収は約510万円、関関同立卒は約492万円となっており、大差ありません。両者とも日本全体の同世代平均(約460万円)より高く、早慶(約602万円)には及ばないものの十分に高収入層に属します。つまり、どちらの大学群でも卒業後に比較的高い給与を得ている人が多いことがわかります。
就職率自体も非常に高く、両グループとも就職希望者の95〜99%が就職を実現しています。例えば関西学院大学の2023年度就職率は99.7%、同志社大学99.5%、明治大学や青山学院大学も毎年98〜99%前後に達します(大学公表値)。
このように「就職できない」という不安は杞憂と言えるでしょう。
業界別の就職実績を見ると、大学や地域による特色が現れます。関関同立は所在地の関西経済圏の影響もあり、製造業(メーカー)への就職割合が高い傾向があります。
例えば関西大学では就職者の業種トップが製造業、次いで情報通信業、小売業となっており、この3業種で過半数を占めます。関西学院大学も製造業が最多、次に金融・保険、情報通信が多く約半数。同志社大学も製造業やIT系が中心で、パナソニックや村田製作所など関西の大手メーカーに多数の採用があります。一方で理工系学生の約58.5%が大学院進学する(=学部卒では就職しない)という特徴も同志社には見られます。
MARCHも全体的には金融(銀行・証券・保険)やメーカーへの就職が多い傾向です。(参照:job-tryout.com)
東京は本社を置く企業が多岐にわたるため、業種の分散傾向もありますが、特に銀行・証券など金融業界は根強い人気があります。大学別にみると青山学院大学はANA・JALなど航空業界への就職が目立ち、国際系学部の強みを活かしたキャビンアテンダントやグローバル職での活躍が多いようです。
中央大学は国家公務員や地方公務員への就職者が伝統的に多く、司法試験や公務員試験に強い法学部の実績が就職にも表れています。明治大学や法政大学は大手メーカー・金融・情報通信など満遍なくOB・OGを送り出しており、NTTやKDDI、メガバンク(三菱UFJ銀行など)では毎年MARCH各校から数十名単位の新卒が採用されています。例えば三菱UFJ銀行では、立教大学から30人、中央・青学から各28人(2019年卒実績)といった具合です。(参照:job-tryout.com)
大学別の主な就職先企業を見ると、就職支援の充実ぶりがうかがえます。同志社大学は直近10年間で国家公務員513名輩出。公共分野に強く、関西学院大学も公務員志望が多いです。また同志社や立命館は関西電力や大阪ガスなどインフラ業界にも多くの卒業生を送り出しています。MARCHでは明治大学がトヨタ自動車や日立製作所など製造業から東京海上日動・野村證券といった金融まで幅広い内定実績を持ち、青学・立教は電通や博報堂などマスコミ、エンタメ系企業にもOBが多いなど、「業界ごとの強み」もあります。(参照:pharos21.net)
こうした就職実績の厚さが卒業生のキャリアを支えており、「MARCH/関関同立卒は就職で有利」という評判につながっています。実際、「就活市場でMARCHと関関同立はどっちが上?」という問いには答えづらく、「少なくとも有名企業への内定率や収入面では差がない」と結論づけられます。3割前後が有名企業に入るこれらの大学群の学生は、就職市場において十分高い競争力を持っているのです。(参照:reashu.com)
徹底比較【大学生活】
キャンパス環境や学生生活の雰囲気は、東のMARCHと西の関関同立で異なる面があります。首都圏のMARCHは都心部にキャンパスを構える大学が多く、都会的で利便性の高い学生生活を送れるのが魅力です。例えば青山学院大学は渋谷駅徒歩圏という抜群の立地、明治大学や法政大学も新宿・市ヶ谷など都心キャンパスが中心です。立教大学も池袋に主要キャンパスがあり、東京のダイナミズムを肌で感じながら学べます。
一方、関関同立は関西の都市近郊に広大なキャンパスを構えるケースが多く、緑豊かな環境で落ち着いた大学生活を送れる点が特徴です。関西学院大学の上ヶ原キャンパスや同志社大学の今出川キャンパスなど、芝生の中庭や歴史的建築が学生の憩いの場になっています。京都・奈良など歴史都市へのアクセスも良く、関西文化を満喫しやすいでしょう。
通学の利便性では東京の大学に軍配が上がります。多くのMARCH各校は最寄駅から徒歩圏にキャンパスがあり、アルバイトや企業インターンにも通いやすいです。中央大学の多摩キャンパスのように郊外にある例もありますが、その場合でも都心キャンパスを別に持つなどカバーしています。関関同立では同志社大今出川キャンパス(地下鉄駅直結)や立命館大大阪いばらきキャンパス(JR駅近接)のように便利な所もありますが、関西学院大(最寄駅からバス利用)など郊外型のところもあります。例えば関学の西宮上ケ原キャンパスはアクセスに難がある反面、美しい景観で受験生にも人気です。関西大学の千里山キャンパスは阪急電車の駅に近く、大阪都心への移動も20分程度と遊びにも便利な立地です。
学生の地域構成にも違いがあります。関関同立は地元(関西)出身者の割合が高い傾向で、例えば関西大学は約81.6%が関西出身(大阪府出身だけで学生の約半数)というデータがあります。関西弁が飛び交いアットホームな雰囲気が醸成されている反面、立命館大学のように全国募集に力を入れ関西圏外出身が約50%に達する大学もあります。
一方、MARCHは首都圏出身者が多いものの全国からの志願者も集まりやすく、地方出身者も一定数います。特に地方の優秀層が「東京で学びたい」とMARCHを目指すケースも多く、結果として関関同立に比べ学生の出身地の多様性がやや高いと言えます(※例えば立教大学は地方高校からの進学者も多い傾向があります)。このためMARCHのキャンパスでは首都圏カルチャーと様々な地方出身者の文化が交錯し、刺激的な人脈が築けるでしょう。
課外活動や学風にも各校の個性が光ります。スポーツ面では、MARCH・関関同立ともに伝統的に強豪クラブを持ちますが、例えば関西学院大学はアメリカンフットボール部が全国優勝の常連として有名です(関学ファイターズ)。MARCHでは青山学院大学が箱根駅伝での活躍が記憶に新しいでしょう。文化系では、立教大学や同志社大学はミッション系らしくクリスマスのイベントが盛大だったりと特色があります。総じて関西の大学は「お祭り好き」で学園祭も地域を巻き込んで盛り上がる印象です。関西大学の最寄り「関大前」駅周辺には夜遅くまで学生で賑わう居酒屋やカラオケが並び、キャンパス外も学生街として発展しています。
一方、東京は街そのものが巨大な遊び場であり、サークル活動以外にもアルバイトやショッピング、ライブなどキャンパス外の刺激が多彩です。都会の中で自主性を磨きたい人にはMARCHの環境が合うでしょう。
インターンシップの機会については、企業本社が集中する東京に立地するMARCHの方が学期中でもインターンに参加しやすい利点があります。大学キャリアセンター主催の業界研究や企業とのコラボ企画も首都圏の大学の方が数多く開催される傾向です。もっとも、関関同立の学生も就活期には大阪など都市部でインターンに参加できますし、近年はオンラインインターンも普及していますから大きな差はありません。ただ在学中の企業アルバイトなどは東京の方が種類も豊富で、早い段階から業界経験を積みたい人には有利と言えます。
徹底比較【卒業後の進路】
大学院進学や留学といった進路でも、大学間の違いがあります。理系学生の大学院進学率は全国的に高いですが、同志社大学では上述の通り理工系の約6割が大学院進学するなど顕著です。
立命館大学や関西大学でも理系は4割前後が大学院に進む傾向にあります。一方、文系では大学院進学者は少数派で、これはMARCHも関関同立も共通しています。中央大学は法科大学院への進学者が多い程度で、基本的には就職がメインです。したがって、「大学院進学前提で腰を据えて研究したい」という人は、同志社大学のように大学院まで一貫した環境が整っている大学や、研究設備の充実した理工系学部を持つ大学を選ぶのも一案です。
海外留学制度の充実度もチェックポイントです。いずれの大学も多数の海外協定校を持ち、交換留学や派遣留学のプログラムを提供しています。特に立命館大学は「スーパーグローバル大学」として世界的な教育研究を推進し、英語で学位取得できる課程を持つなどグローバル化に積極的です。関西学院大学も留学生受入が盛んで英語教育に力を入れており、TOEIC高得点者が多いとも言われます。
MARCHでは青山学院大学や立教大学が英語・国際系に強く、長期留学する学生も多く出ています。明治大学は全学生の1割留学を目標に掲げるなどグローバル人材育成に注力しています(留学奨学金制度も豊富です)。総じて「在学中に海外経験を積みたい」という希望は、どの大学でも十分叶えられます。ただ、交換留学の競争率や語学研修の特色は大学によって異なるため、希望する国・地域やプログラムがあるか事前に各大学の国際センター情報を比較すると良いでしょう。
どちらを選ぶべきか?判断基準とアドバイス
MARCHと関関同立、どちらを選ぶべきかは、最終的にはあなたが大学生活において「何を重視するか」によります。
学ぶ場所と就職圏域
大学の所在地は4年間の生活環境だけでなく就職活動にも影響します。自分が首都圏での就職を志望するならMARCH、関西を志望するなら関関同立という基準で選びのが良いでしょう。一般的に地元志向の学生が多いため、関関同立の学生が関東の企業に就職する数はMARCHより少ない傾向があります。
関西圏での評価はMARCHと同等以上ですが、関東圏では知名度・評価ともMARCHと同程度であっても物理的距離のハンデがあります。東京の企業は「関関同立」という大学群も人事担当者は把握しており評価は高いものの、どうしても採用人数は地理的に近いMARCHの学生の方が多くなるのが実情です。
逆に関西で就職したい場合、地元企業からの認知やOBネットワークが太い関西同立の方が有利な場面もあるでしょう。
大学の看板学部・分野
志望する学問分野がその大学の看板学部かどうかも重要です。
例えば、法律・政治に強い中央大・法政大、公認会計士なら明治・同志社、英語なら青学・関学、国際関係なら立教・立命館、理工系なら同志社・明治・立命館…といった具合に、それぞれ強みの分野があります。学部レベルで特殊な専攻を求めるなら、設置の有無も確認しましょう(例:関学と同志社には神学部がありますがMARCHには存在しない、明治には農学部があるが関関同立にはない、など)。
大学ブランド・偏差値
一般的な偏差値やブランドイメージも無視できません。関西では「同志社>関学≒関大>立命」の序列観があり、東京では「明治≒立教≒青学>中央>法政」のような雰囲気があります。ただしこの差は僅かなもので、就職市場ではほぼ同格と見なされます。強いて言えば、「関西トップ私大の同志社」は別格感がありますし、「MARCHトップの明治」も就職に強いイメージがあります。自分が「看板大学」にこだわりたいならその点も考慮に入れると良いでしょう。
キャンパスライフの好み
4年間を過ごす環境として、都会の真ん中で刺激を受けたいか、それとも落ち着いた学園都市でじっくり学びたいかは大きな違いです。東京のMARCHはキャンパスが分散しがちで通学に電車移動が伴うケースもありますが、その分アルバイトやイベント参加など行動の幅が広がります。関関同立は総合キャンパスに生活の大半が集約される分、サークルや友人付き合いが濃密で「THE大学生活」を送りやすいです。どちらが自分に合うか想像してみましょう。
将来のキャリア目標
入りたい業界や企業が決まっている場合、そのOB・OGネットワークを調べてみるのも有効です。例えば航空業界志望なら青学有利、公務員志望なら中央大や同志社大に実績多数、関西のメーカー志望なら同志社大や関西大OBが多い、などの違いがあります。もっともネットワークは絶対条件ではないので、所在地やインターン機会など前述の要素も含め総合判断しましょう。
まとめ
結論として、MARCHと関関同立は「東の雄」「西の雄」として互いに肩を並べる存在であり、偏差値・就職・教育環境のいずれも大きな差異はありません。したがって「自分の志望分野で強い大学」「自分が4年間を送りたい土地」を基準に選ぶのが賢明でしょう。
- 「将来は東京の企業でバリバリ働きたい」→迷わずMARCHを目指す(就活コスト含め有利)
- 「関西で腰を据えてキャリアを築きたい」→関関同立でネットワークを築く(地元就職なら評価◎)
- 「この分野なら負けたくない」→その分野の看板学部を持つ大学(例:法学志望なら中央 or 関大)
- 「国際的な環境に身を置きたい」→SGU採択の立命館や留学に強い青学・関学
- 「憧れのキャンパスライフ」→都心のおしゃれキャンパス(青学・立教・関学など)か、伝統薫る歴史キャンパス(同志社・明治など)か
といった観点でマッチする大学を選ぶと良いでしょう。
いずれの大学群も世代全体の上位15%前後の学生が集まる高水準な環境にあり、得られるチャンスも多分に用意されています。あなたの希望にフィットする大学を選び抜き、充実した学生生活とその先のキャリアへの土台を築いてください。頑張る受験生を応援しています!