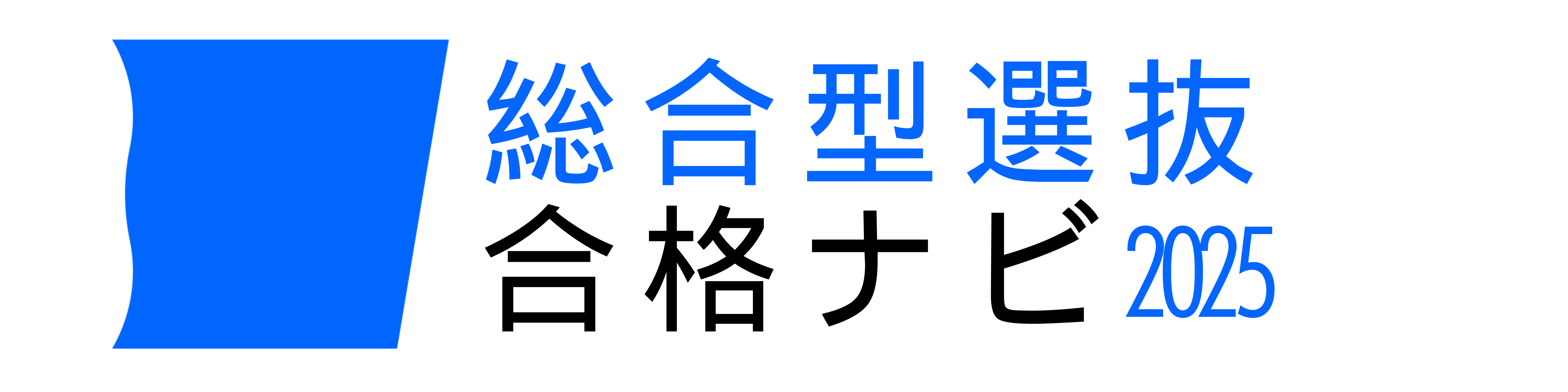こんにちは!大学受験で迷われている方、特に「総合型選抜って何だろう?」と疑問をお持ちの皆さんに向けて、総合型選抜の基礎知識から合格のコツまでを徹底解説します。
近年、大学入試において総合型選抜の存在感が急速に高まっています。「ずるい入試」「勉強しなくても受かる入試」などと誤解されることもありますが、実は総合型選抜こそが、これからの時代に合った大学入試なのです。
この記事では「総合型選抜とは何か」という基本から、なぜ今総合型選抜が注目されているのか、どうすれば合格できるのかまで、詳しく解説していきます。
総合型選抜での大学受験に興味がある!
一般入試しか考えてなかったけど総合型選抜にも興味が出てきた!
大学受験、怖い…
そんな風に感じている方は最後まで本記事を読んでいただけると、その後の大学受験を上手く進めれるようになるかと思います。

総合型選抜が今話題になっている背景
「総合型選抜」という言葉をよく耳にするようになりました。テレビのニュースやSNSでも「ずるい入試」「勉強しなくても受かる入試」などと取り上げられることがありますが、なぜこれほど注目されているのでしょうか?
その背景には、現在の受験生を取り巻く日本の教育環境の変化があります。総合型選抜での大学受験合格者が急増している理由は主に3つあります。
背景1|一般入試の難化
かつては「王道は一般入試」というイメージが強く、「推薦の生徒は受験勉強をしていないから大学に入ってからは勉強についていけないんじゃないか?」といった誤解もありました。実際、数年前までは一般入試の割合が学校推薦型選抜(指定校・公募・学校推薦)を含めても全体の大半を占めるメジャーな入試でした。
しかし近年、センター試験から共通テストへの移行に伴う数学や一部科目の難化、情報・総合などの新設科目の増加、英語4技能重視や民間試験活用の流れなどにより、一般入試のハードルが上がっています。
倍率を見ても、例えば有名大学の学部では、一般入試の倍率が総合型選抜や公募推薦より高いケースが増えています。一般入試だけでは志望校合格が難しくなってきていることが、総合型選抜が人気を増している主な要因と言えるでしょう。
背景2|都内私立大学の定員問題
少子高齢化により「大学入試は易しくなる」というのが一般的な予想でしたが、実際には逆の現象が起きています。
都内大学を中心に学部の新設や既存学部の増加に対する取り締まりが強くなり、大学はこれ以上入学者定員を増やすことが難しくなっています。一方で、少子化・賃金の低迷・景気の低下やコロナの影響で、名の通った大学に入りたいという学生は増えているのです。
特に日東駒専・GMARCH・早慶上理などの都内私立大学の人気が上昇し、競争率が高まっています。少子化どころか、難関大学の人気は上がるばかりで、入試の競争率も上昇傾向にあります。
このような状況から、受験生は複数の入試形式に出願し、合格率を極限まで引き上げることが必要になってきました。
背景3|就活の早期化
就職活動の早期化も、総合型選抜人気の背景にあります。一見、大学にも合格していない段階で就活を考えるのは不思議に思えるかもしれませんが、実は就活と総合型選抜には深い関係があるのです。
従来、大学3〜4年からスタートが恒例だった就活ですが、経団連が就職活動の早期化を認めたことで、その開始時期がどんどん早まっています。大学1年生のうちから長期インターンに取り組む学生が有利に大手内定を掴むなどの変化も見られます。
これは企業が即戦力になりうる実務能力を持つ学生を求めているからです。経済産業省も「社会人基礎力」として人材の目標方針を定めています。
大学は本来研究機関ですが、このような社会の変化を受けて、入学時点から高校生の実務能力や社会人としての総合的な能力を求めるようになりました。面接やプレゼンテーションが総合型選抜で広く取り入れられているのもそのためです。
これらの理由により、多くの大学が総合型選抜の定員枠を拡大しています。早稲田大学や慶應義塾大学などの難関私立大学も今後、総合型選抜などの推薦入試での合格者割合を増やす方針を示しており、一般入試だけに頼る受験戦略は時代遅れになりつつあります。
総合型選抜とは?基礎知識の徹底解説
総合型選抜とは、大学が「求める学生像」に合致する人物を選抜する入試制度です。以前は「AO入試」と呼ばれていました。AO入試はAdmission Office(アドミッション・オフィス)入試の略で、受験生の人物像と大学の求める学生像(アドミッション・ポリシー)がどれだけ合っているかで合否が決まる入試形態です。
総合型選抜の基本構造
総合型選抜は通常、次のような流れで実施されます。
まず一次審査として、志望理由書・英語資格・評点・推薦状などの書類審査が行われます。この段階で選考を通過すると、二次試験として面接・小論文・プレゼンテーションなどが実施されます。一部の大学(特に国公立大学)では限定的な学力試験や口頭試問が課される場合もあります。
従来のAO入試との主な違いは、基礎学力や学校での成績、小論文の得点により重点が置かれるようになったことです。以前のAO入試では学校での基礎的な勉学への取り組みや英語能力をあまり重視していなかったため、大学進学後に授業についていけない学生が少なくありませんでした。
こうした課題を解決するため、現在の総合型選抜では「調査書等の出願書類だけでなく、大学独自の評価方法(小論文、プレゼン、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテストなど)もしくは大学入学共通テストのいずれか一つの活用を必須化する」というルールが設けられています。
しかし、依然として総合型選抜は指定校や公募推薦よりも自由度が高く、ほぼ全ての高校生に出願のチャンスがあると言えます。また、他の入試と合わせて複数入試で同じ学部に出願できる場合もあり、戦略的な受験が可能です。
入試形態の種類と特徴
総合型選抜をより深く理解するには、他の入試形態との違いを知ることが重要です。ここでは主な入試形態の特徴を比較していきましょう。
指定校推薦
指定校推薦は、高校在籍中の成績優秀者が対象となる入試形態です。校内の選考に合格すれば、書類試験や面接はありますが、ほぼ100%の確率で年内に大学進学を確定させることができます。受験には学校長の推薦が必要で、合格した場合は辞退が許されない専願制となっています。
大学と高校の取り決めによって「その高校から特定大学に進学する枠」が付与されており、3年間コツコツと勉強して高い評点平均(一般的に4.8程度)を維持していれば、ほぼ間違いなく合格できます。
ただし、国公立大学には指定校推薦枠は存在しません。また、自分の高校に志望校・志望学部の指定校推薦枠がない場合はこの制度を利用できません。さらに、進学実績を良くするために、通常の入試で合格可能性が高い生徒には指定校推薦枠を与えない高校もあります。
志望校の枠が高校に存在し、かつ評点平均が高い生徒に限定的におすすめの入試方法と言えるでしょう。
公募推薦
公募推薦は指定校推薦と似ていますが、より開かれた形式です。こちらも合格した場合は辞退が許されない専願制で、学校長の推薦が必要です。指定校推薦に加えて、学力試験や追加の提出書類がある大学も多く、競争率も高くなります。
上智大学などは事実上総合型選抜が存在せず、公募推薦が類似する受験方式となっています。指定校推薦枠が自身の高校にはないが似たような入試にチャレンジしたい場合や、学校の成績が良く年内に入試を終わらせたい学生に向いている入試形態です。
指定校推薦と公募推薦は合わせて「学校推薦型選抜」と総称されることもあります。どちらも学校での好成績と学校長の推薦が必須のため、校内で素行が悪い学生や通信制の生徒、不登校の学生には受験のチャンスがないという制約があります。
総合型選抜
総合型選抜は指定校や公募推薦と違い、学校長の推薦状が不要です。そのため校内選考はありません。代わりに「評価書」と呼ばれる学校での成績や出席率などについて記載した書類を提出します。
また、併願可能な大学が多く、評点平均が低くても出願できる大学もあります。例えば、慶應義塾大学SFCや中央大学チャレンジ入試などは、英検や評点の制限がありません。
旧AO入試からの変更点としては、前述したように基礎学力の確認が必須になったことや、学校での成績、小論文の得点に比重が増した点が挙げられます。
総合型選抜の最大の特徴は、指定校や公募推薦よりも自由度が高く、ほぼすべての高校生に出願のチャンスがあることです。他の入試と合わせて複数入試で同じ学部に出願できる場合もあるため、戦略的な受験が可能となります。
一般選抜
一般選抜は最も伝統的な入試形態です。国公立大学では共通テストの受験が必須で、特定の科目の学力試験を複数受験します。
近年は民間英語資格試験の成績によって加点が得られる大学も増えており、英語の比重が高くなっています。暗記や情報処理に自信があり、じっくり勉強できる高校生に適した入試と言えるでしょう。
この他にも、海外からの帰国生を対象にした帰国子女入試や、国際バカロレアのスコアで評価するIB入試、一部大学に限りますが高校3年生でなくても飛び級で出願できる特色入試など、様々な入試形態が存在します。
入試形態の多様化により、総合型選抜を中心としながら、他の入試形態も組み合わせた複合的な受験戦略を立てることが可能になっています。これにより、志望校への合格率を最大化することができるのです。
令和時代の高校生が直面する大学入試の現実
令和の高校生は、急速に変化する社会の中でさまざまな課題を背負わされています。センター試験から共通テストへの移行に伴う数学の難化、情報・総合などの新設科目の増加、英語4技能習得の必須化など、昭和・平成時代とは比較にならないプレッシャーにさらされています。
現代社会では「英語はできて当たり前」「GMARCH以上の大学に行くのが当たり前」という風潮があり、名の通った大学に進学できなければ、都内での大手企業への就職も厳しい状況です。若干22歳までの経歴が、その後の人生設計や収入を大きく左右する時代になっているのです。
「大学にとりあえず行っておけばいい」という考え方は、短大卒でも銀行に採用されていた昭和時代を生きてきた40〜50代の方々の時代遅れな発想にすぎません。現実は厳しく、大学入試は年々難化し、高校生たちは逆風の中で自分の将来を決める選択を迫られています。
近年では国公立大学の多くや私立大学の相当数が総合型・推薦選抜による入試を重視するようになりました。一方でメディアでは「総合型選抜で学力低下が進む」「公平性に欠ける入試だ」といった批判的な見方も報じられています。
しかし、貧困から抜け出したい、地方の限られた環境から飛び出したいと必死に頑張る高校生たちにとって、総合型選抜の是非を論じることはあまり意味がありません。彼らが本当に知りたいのは「自分は志望校に合格できるのか」「将来、充実した人生を送れるのか」というシンプルな問いなのです。
高校生たちは複雑な社会情勢や入試制度の変化に翻弄されながらも、自分の未来を切り開くために懸命に努力を続けているのです。
高校生なら絶対気になる|総合型選抜で合格する方法
総合型選抜で合格するためには、一般的に次の3つの要素を準備することが重要です。
① 提出書類:志望理由書、英語資格、評点平均などを含む
② 小論文:論理的思考力と文章力が問われる
③ 面接:コミュニケーション能力やその場での対応力が問われる
これらを一つ一つ数学や美術のような「科目」として捉えると分かりやすいでしょう。通常、提出書類が一次試験、その後に小論文や面接を含む二次試験という構成になります。したがって、まずは一次試験を突破するための対策が必要です。
そして最も重要なのは、これらの対策に「早期に」取り組むことです。特に評点と英語資格については、中学生〜高校1年生での早期かつ定期的な勉強が必須となります。
評定平均と英語資格の重要性
評定平均と英語資格は総合型選抜の基礎となる要素です。大学によって評定や英語資格で足切りを設けているところも多いため、評定3.8以上、英検2級の取得はスタンダードと言えます。これが難しい場合でも、評点3.5以上、英検準2級は取得しておきたいところです。
評点が重視される傾向が強まっている背景には、研究者としての素養が高い生徒を大学が求めているという事情があります。大学は研究機関であり、研究には長期的にコツコツと一つのテーマに向き合う姿勢が必要です。コツコツ勉強したり幅広い教養を身につけたりする意欲の表れとして、評点の高さは高く評価されるのです。
これらの基礎要素を早めに確保しておかないと、高校3年生の部活引退や最後の定期試験などで忙しい時期に、英検の勉強や成績向上のための対策まで行わなければならなくなります。余裕のある時期にしっかり取り組んで足切り基準をクリアしておき、高校3年生になってからは志望理由書や小論文の練習に集中するのが理想的です。
志望理由書の重要性
総合型選抜における最も重要な要素の一つが志望理由書です。多くの受験生はこれを単なる作文や自己PR書類と捉えがちですが、それは大きな誤解です。志望理由書は「研究計画書」と言い換えることができます。自己PRだけでなく、大学で予定している研究内容や将来の具体的なキャリアプランについても述べる必要があるのです。
「私は大学のここが好きだし、合うと思うから行きたい!」といった単純な志望動機では、合格水準には到底届きません。
では、なぜ志望理由書に早期から取り組む必要があるのでしょうか?その理由は「志望理由書に嘘がないことの証明」をするためです。志望理由書はただの書類ですから、やろうと思えば代筆も可能で、虚偽の経歴や考えを書くこともできてしまいます。
こうした「脚色」の可能性を排除するための要素が、課外活動や探究実績です。合格する学生の多くは、志望理由書の中に過去の特別な活動や取り組みについて記載しています。高校3年生の大学受験直前になって突然志望校や興味分野が見つかったのではなく、それ以前から一貫して興味を持ち、活動してきたことを示す必要があるのです。
つまり、学校や学習塾主催のスタディーツアーや有名人の講演やイベントに参加したなどといった課外活動は全く評価されません。かえって悪印象で不合格になってしまう場合もあります。ブルーアカデミーはもっと本質的な指導をしますが、スタディーツアー商品を営業するためにそういうアドバイスをする塾も存在しますので気をつけてください
課外活動や探究実績は、その学生の興味や能力が一時的なものではなく、長期的に培われてきたものであることを証明します。そのため、まず活動を積み重ね、その過程での気づきや成長、現時点での限界などを言語化し、それを踏まえて大学でさらに学びたいことを志望理由書に書く必要があります。
活動に一貫性がなかったり、受験直前に急いで活動実績を作ったりすると、「興味が定まらない学生」「受験のためだけに活動している学生」という印象を与えてしまいかねません。したがって、志望理由書に書くための内容・言語化・活動の準備は、高校低学年など早い段階から始めることが理想的です。
ただし、高校2年生や3年生になってから総合型選抜に取り組み始めても、適切な対策を行えば十分に合格できる可能性はあります。しっかりとした戦略と努力によって、失われた時間を取り戻すことができるのです。
今から総合型選抜に逆転合格する3つの方法
高校2年生や3年生からでも、適切な対策を行えば総合型選抜での合格は十分に可能です。ここでは、今から総合型選抜に逆転合格するための3つの方法を紹介します。
1. 基礎学力の底上げ
基礎学力の底上げには主に、評定平均と英語資格スコアの向上が含まれます。評定平均は3.8以上、できれば4.2以上を目指し、英語資格は英検2級以上(準1級以上がより望ましい)の取得を目標としましょう。
また、抽象化能力(様々な事象を理論的に考える力)も基礎学力の一つとして重要です。これらの基礎学力を向上させるためには、苦手科目の克服に取り組むことが必要です。
ただし、注意したいのは「塾に通い詰めよう」という考え方です。一般入試や英語の勉強については、すでに多くの専門的な参考書や対策方法が確立されており、比較的安価にそれらを入手できます。自分の実力を正確に把握し、スモールステップな目標を設定して、学校での勉強も含めて着実に進めていくことが大切です。
2. 日本語4技能の訓練
総合型選抜では日本語の能力も重視されます。具体的には次の4つの技能が問われます。
・Reading(読解能力):日本語文章の速読、要約、題意分解ができること
・Writing(論述能力):日本語を用いた論理的な文章が書けること
・Speaking(対話能力):プレゼンや面接で適切な受け答えができること
・Listening(面接能力):面接での質問の意図を瞬時に理解できること
総合型選抜は「面接でうまく話せば合格」「書類審査を突破すれば余裕」と思われがちですが、それは誤解です。近年は小論文などを通じて、日本語での論理的思考力や表現力もしっかりと評価される傾向が強まっています。
これらの4技能を向上させるには、主に小論文対策を通じた訓練が効果的です。実際の入試問題を解いてみる、論理的な文章構成を学ぶ、時事問題について自分の意見をまとめるなどの練習を重ねることで、日本語の運用能力を高めていきましょう。
3. 研究テーマの発見
研究テーマとは、大学に入ってから4年間かけて学習し、研究に取り組んでいくテーマのことです。言い換えれば、卒業論文のテーマとも言えるでしょう。大学は教育機関というよりも研究機関であるため、入学時点で4年間の研究計画や目標を持ち、それについて説明できることが求められます。
良い研究テーマには以下の要素が必要です。
・学術性:学問を用いて探究する必要性がある領域であること
・自己唯一性:あなた自身がそのテーマを研究する意義が感情的かつ論理的に存在すること
・競合優位性:一般的な高校生と比較して独自性のあるテーマ設定ができていること
研究テーマの発見は非常に重要です。ありきたりな内容や熟考されていないテーマで出願すると、高確率で一次書類審査の時点で不合格になってしまいます。
特に研究テーマは、低学年から方向性を定めておいた方が受験に有利です。研究テーマが決まっていない段階で志望理由書を何度も書いてみたり、漠然と受験対策をしたりしても、合格には近づけません。受験では、意味のある努力を適切な量こなすことが大切なのです。
総合型選抜の対策スケジュール
総合型選抜で逆転合格を目指すなら、以下のステップを踏むことが重要です。
1. 現状の徹底分析
まず自分の現状を客観的に分析しましょう。現在取得できそうな英語資格のレベル、評定平均をどこまで上げられそうか、活動実績はあるのか、これから作れそうか、小論文でしっかり得点できるかなどを検討します。自分の強みと弱みを正確に把握することで、効率的な対策が可能になります。
2. 目標・受験校決定
次に、具体的な目標と志望校を決めましょう。「絶対に国公立を目指す」「MARCH以上を目指す」「現役合格を目指す」などの目標と、具体的な志望校を暫定的にでも決めておくことが大切です。目標があることで、日々の勉強や活動に意義が生まれます。
3. 合格者の志望理由書分析
実際に総合型選抜で合格した先輩たちの志望理由書を分析することも効果的です。自分の志望校でなくても、様々な大学の合格者の書類を読み、どのようなステータス(評点、実績、英検など)から逆転合格したのかという事例を知ることで、自分の戦略を立てる参考になります。
4. 小論文速解き訓練
小論文は総合型選抜の重要な試験科目の一つです。過去問や模擬問題を時間を計って解く訓練を重ねることで、論理的思考力と文章力を鍛えましょう。単に書くだけでなく、添削を受けることで、自分の弱点を把握し改善することが重要です。
5. 面接質問練習
面接では、「志望理由」「学部選択の理由」「将来の展望」など、よく聞かれる質問があります。これらの質問に対する回答を準備し、実際に声に出して練習することで、本番での緊張を和らげ、自分の考えを明確に伝える力を養いましょう。
特に重要なのは、これらの対策を計画的に進めるためのマインドセットです。「なんとなく受験」「なんとなく浪人」という姿勢では、後から大きな代償を払うことになります。サボればサボるほど、より高い塾費用、より大変な努力、より大きな将来への不安が待っています。
目標を定め、自ら受験に関する情報を収集する姿勢こそが重要です。周囲と一歩差をつける行動を自ら起こせる学生が、最終的に合格をつかみ取るのです。
総合型選抜の4つの本当のメリット
総合型選抜について語られる主なメリットは以下の7つですが、このうち最初の4つは比較的正確な情報です。
①受験機会が増える
②準備や対策を通じて学びたいことや将来が定まる
③自分の強みや特技を活かせる
④年内に受験が終了する
⑤倍率が低く、チャンスが多い
⑥浪人生や通信制の学生にもチャンスがある
⑦そこまで勉強をしなくても良い
それぞれ見ていきましょう!
①受験機会を増やせる実質的なメリット
総合型選抜と一般入試を併用すれば、第一志望校に複数回チャレンジできます。公募推薦・学校推薦選抜も併用可能な大学なら、さらに機会が増えます。志望校が明確でない場合も、同レベルの大学に複数出願しやすいメリットがあります。
一般入試での複数出願は各大学別の対策が必要ですが、総合型選抜なら書類の内容を調整するだけで一次試験突破の可能性があり、「まとめて出願」のハードルが低いのです。また、難関大学を目指す場合、総合型選抜で安全圏の合格を確保してから、残りの期間を第一志望校対策に集中できます。
②③将来ビジョンを具体化できる貴重な機会
一般入試では「受かりそうな大学」への志望が中心になりがちですが、総合型選抜では大学のアドミッションポリシーやカリキュラム研究を通じて、「大学で何を学べるか」を深く考える機会が生まれます。それにより受験のモチベーション維持も容易になります。
ただし注意点として、「自己分析」や「価値観診断」と称した時間のかかる対策が塾などで行われることがあります。18歳で将来を完全に決める必要はなく、「受験用の志望理由」があれば合格可能なので、過度なプレッシャーを感じる必要はありません。
また、「特別な才能を伸ばす」といった甘い言葉には惑わされないことが大切です。単に留学や生徒会活動といった経験だけでは不十分で、大学での研究計画に沿った探究活動の履歴が重要になります。
④早期に進路が決まる大きなアドバンテージ
私立大学なら年内に、国公立大学も12〜1月には大半の受験が終わるため、早めに次のステップに進めます。「受験から解放されたい」という思いだけでなく、合格後すぐに研究・起業・インターン等の活動を始められる点や、奨学金申請の準備時間が確保できる点も大きなメリットです。大学生活を計画的に過ごしたい学生にとって、この数ヶ月の差は重要な意味を持ちます。
誤解されやすい3つの「メリット」の真相
残りの3つについては、限定的な条件下でしか当てはまらないケースが多く、注意が必要です。
⑤「倍率が低い」は必ずしも正確ではない
確かに一部の学部・学科では低倍率の入試もありますが、それはニッチな分野で志願者そのものが少ないケースも多いです。人気の学部では10倍を超える倍率になることも珍しくありません。
ただし、倍率を過度に心配する必要もありません。「とりあえず出しておく」層も多いため、実質的な競争率はもっと低い可能性があります。また、英語資格保持者向けの特別枠など、条件によって大幅に倍率が下がるケースもあります。
倍率だけで受験校を選定するのはリスキーなことであると覚えていただけると嬉しいです。
⑥浪人生・通信制学生の合格は条件次第
一部の学習塾が強調する「浪人生や通信制学生でも合格できる」という主張は、特別な才能を持つ一部の学生にしか当てはまらないケースが多いです。浪人生の場合、高校時代の評定が悪いと合格は非常に難しく、「浪人中の活動実績」も重視されます。
通信制の生徒は確かに進学の可能性が広がっていますが、「時間の自由度」や「良い成績が取りやすい」というメリットを活かした独自の活動実績や学習成果が求められます。単に評定が良いだけでは、進学校の生徒より有利になるわけではありません。
⑦「勉強不要」は完全な誤解
「そこまで勉強しなくても良い」という主張は完全な誤りです。特別な才能の持ち主か、高額な塾に通える一部の富裕層以外は、一定レベルの学習が必要です。
総合型選抜は「勉強が不要」なのではなく、「別の形の努力が必要」と理解すべきです。自分の過去と今、そして将来とみっちり向かい合うことが必要です。小論文対策や日本語力の向上も含め、従来の受験勉強とは異なる努力が求められます。結局のところ、どんな入試方式でも努力なしで合格できる道はないのです。
まとめ:総合型選抜を活かした大学受験戦略
現在の大学受験環境は大きく変化しています。一般入試の難化、大学の定員問題、就活の早期化などの背景から、総合型選抜はますます重要な入試形態となっています。
総合型選抜は決して「楽な入試」ではなく、むしろ総合的な能力が問われる入試です。合格するためには評定と英語資格の取得、日本語4技能の向上、独自の研究テーマ設定など、計画的な準備が必要となります。
特に重要なのは早期からの対策です。しかし、高校2年生や3年生からでも、適切な戦略と努力、そしてそれを伴走してくれるプロフェッショナルの手があれば逆転合格は十分に可能です。現状を正確に分析し、目標を設定し、合格者の事例を研究しながら、小論文や面接の対策を進めていきましょう。
大学受験はRPGゲームのようなものです。受験を通じて人間的に成長するという側面はあるものの、最終的な目標は志望校合格にあります。そのためには適切な戦略、自己管理、効果的な努力量の確保、良い仲間との切磋琢磨が必要です。
総合型選抜は、勉強だけでなく様々な能力を評価する入試です。自分の強みを活かし、弱みを補いながら、理想の大学進学を実現しましょう。一般入試だけに頼らず、総合型選抜を含む複数の入試形態を戦略的に活用することが、これからの時代の賢い受験方法と言えるでしょう。
いかがでしたか?この記事では「総合型選抜とは何か」という基本から、なぜ今注目されているのか、どうすれば合格できるのかまで詳しく解説しました。大学受験は人生の大きな分岐点です。正しい情報と戦略で、自分の理想の未来へと一歩を踏み出してください!
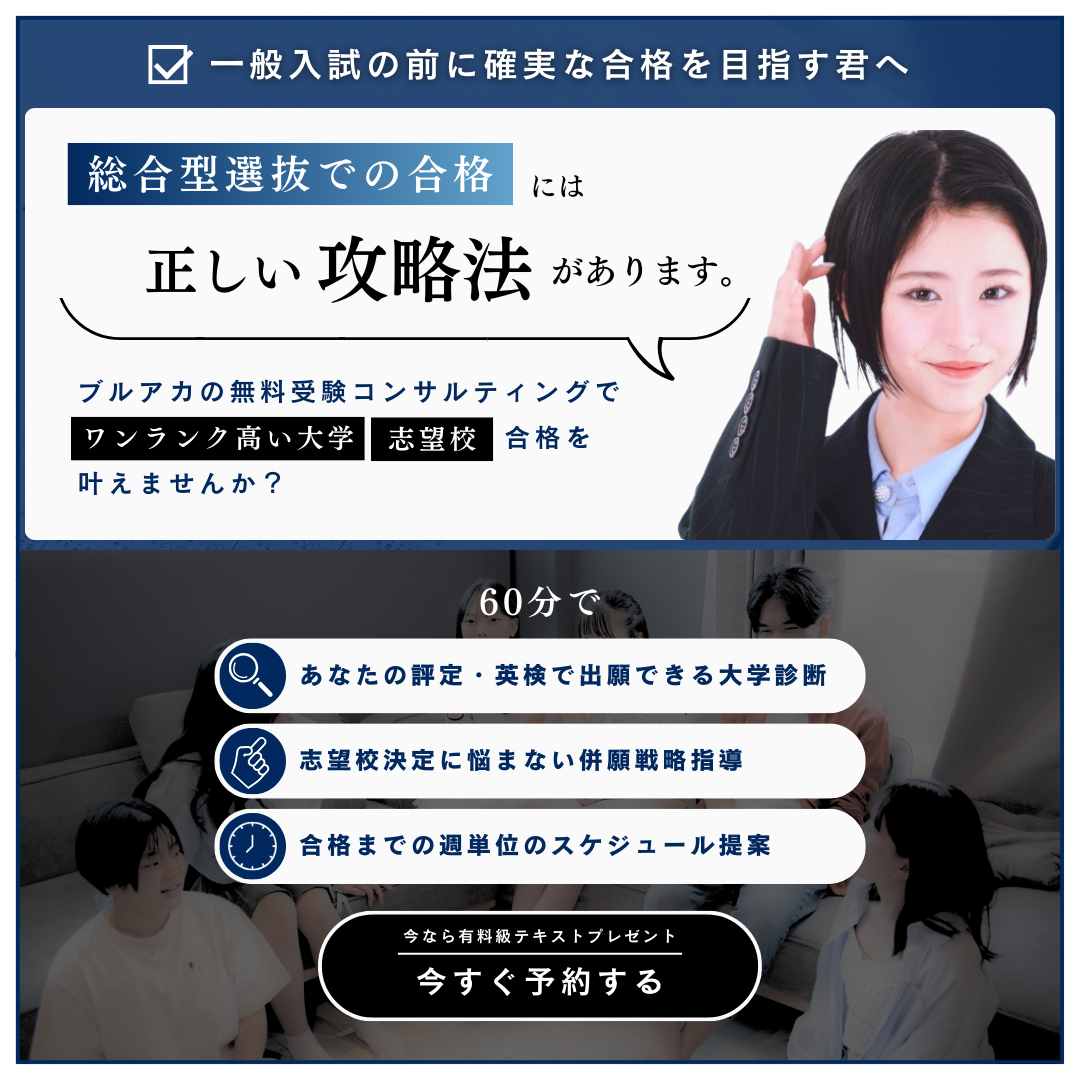

ブルーアカデミー塾長|どんな崖っぷちの学生でも逆転合格させる『神の手』名門城星学園幼稚園/小学校から清風南海中学/高等学校に進学。高校時にはニュージランドに単身留学し、飛び級帰国の後、横浜国立大学経営学部に進学。幼稚園/小学校/中学/大学受験を網羅している受験のエキスパート。関西圏の入試事情や帰国生入試にも精通。